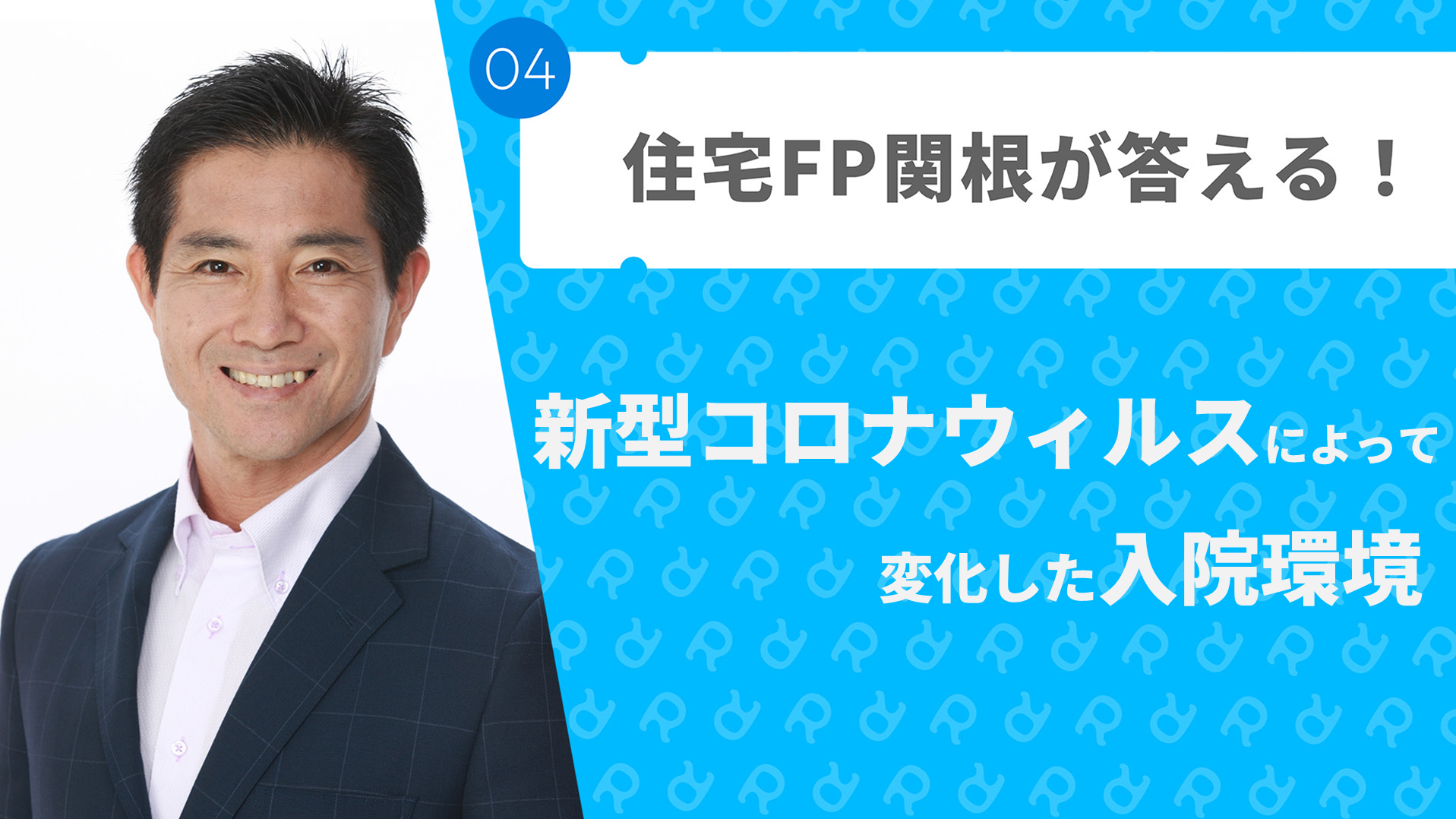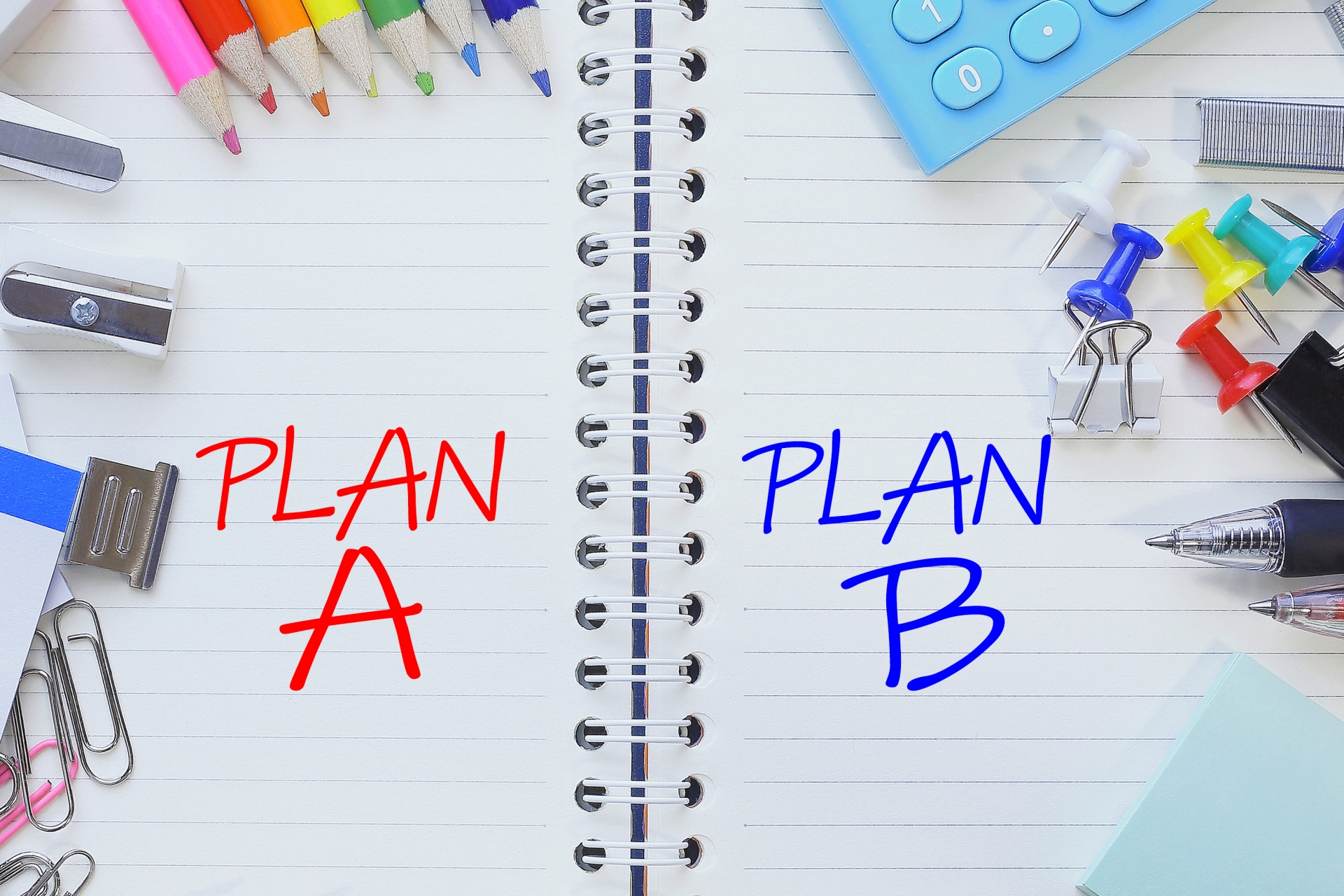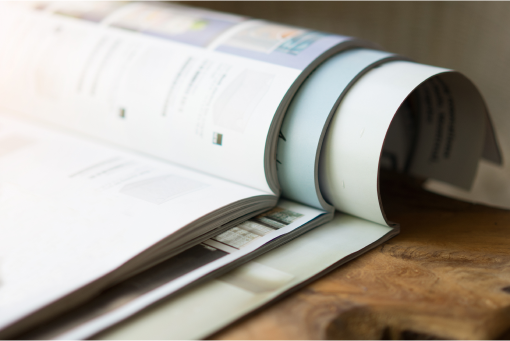生命保険の選び方
2021.09.03
2人に1人ががんになる?最新のがん保険を選ぶポイント
今や日本人の2人に1人が”がん”になる時代と言われています。
がんに備えた生命保険の種類はいくつかありますが、その中でも「医療保険」に入っている方が多いと思います。では、”がん”だけに特化した「がん保険」はそもそも必要なのでしょうか?また、どのくらいの人が加入しているのでしょうか?
今回はがんになる確率と、最新のがん保険の選び方についてお話していきます。
■がんになる確率はどれくらい?
国立がん研究センターの2018年のデータに基づく統計によると、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、男性65.0%、女性50.2%※1です。男女ともに2人に1人以上の確率です。
さらに、日本人ががんで死亡する確率は、2019年のデータにに基づく統計によると、男性26.7%(4人に1人)、女性17.8%(6人に1人)※2です。
日本においては、死因の1位が悪性新生物(がん)です。日本の死因の1位ががんになったのは1981年からで、そこから30年間で死亡数は2倍以上に増えています。
世界的にみても、がんの患者数や死亡者数は増えていますが半数以上が、発展途上国です。アメリカではがんによる死亡者数は毎年減少傾向にある反面、日本は増え続けているのが現状です。日本は先進国で唯一、がんで亡くなる人が増え続けている国なのです。
(※1)(※2) 出典: 国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービスHP>最新がん統計
■がん死亡者が減らないのはなぜ?
ではなぜ先進国の中で日本だけが、がんによる死亡者数が減らないのでしょうか?
がんは早期発見ができれば95%が治る病気とも言われています。したがって、がんによる死亡者数を減らすには早期発見をすることが大切になります。しかし、日本はこの早期発見をするためのがん検診の受診率が米国に比べるととても低いのです。
たとえば、OECD Health Care Utilisation, Screeningの2019年のデータによると日本の乳がん検診の受診率は46%ですが、アメリカは76%です。
また、データ記載があった国の平均受診率は67%。受診率が最も低い国はトルコでしたが、日本はトルコの次に低い受診率でした。日本の乳がん検診の受診率は明らかに低いというのがデータからわかりますね。
そのため、日本では早期発見による早期治療ができる確率が低く、見つかったときにはがんが進行していて残念ながら治せなかった方が多くいると考えられます。
■がん保険の加入率
男女ともに2人に1人以上の確率でがんに罹患するという現状にある日本ですが、がん保険の加入率はどれくらいなのでしょうか?
公益財団法人生命保険文化センターの令和元年度「生活保障に関する調査」(令和元年12月発行)によると、民間の生命保険会社や共済等で取り扱っているがん保険やがん特約の加入率は42.6%でした。平成13年の加入率は21.2%でしたが、それ以降は増加傾向にあり、国民のがんへの備えの意識は上がってきているという事がわかります。
(※)参考:公益財団法人生命保険文化センター>調査報告>生活保障に関する調査
■がん保険を選ぶポイントは?自分にピッタリな保障の選び方
日本人の2人に1人以上ががんになっているという現状からすると、がんは罹患するリスクの高い病気だといえます。リスクが高いのであれば、備えがあった方がもちろん安心です。ではどういった保険で備えるのがいいでしょうか?
がん保険は、がんと診断されたときに一時金としてまとまった給付金が受け取れるものや、がんでの入院や通院に対して給付金が受け取れるもの、放射線治療をした際に給付金が受け取れるものなどがあります。また、公的な医療保険が効かない全額自己負担の高額な治療に対しての治療費を負担してくれるものもあり、保障の内容はさまざまです。
ここでは、最新のがん保険を選ぶポイントをお伝えします。
・通院や在宅療養にも対応できる
昨今の医療技術の進歩にともない、がん治療にかかる入院期間は短くなっています。
がんの治療法としては1.外科療法、2.放射線療法、3.化学療法(抗がん剤)があり、これらはがんの3大治療法と呼ばれています。そのうちの2.3.の治療法は通院をしながら治療を続けていくケースが多いです。
通院や在宅療養であれば、自宅で日常生活を送りながらがんの治療を受けることができます。しかし、その反面、通院のための移動手段の確保をするためにご自身やご家族の負担が増えるのも事実です。
がん保険を選ぶ際には、通院や在宅療養でも給付金が受け取れるかどうかが大切なポイントのひとつです。
・まとまった一時金が受け取れる
がんと診断された時に一時金として100万円や200万円などのまとまったお金が受け取れる保障があれば、想定外の出費にも柔軟に対応ができます。
たとえば、入院期間が2週間と言われていたけど、想定よりも長時間の大きな手術になったことで体への負担が大きくかかり、予定よりも1ヵ月も入院が長引いたというケースもあります。
また、診断一時金は、2年に1回や1年に1回など治療が続いていたら複数回受け取れるタイプが一般的です。ただ注意点として、2回目以降に一時金を受け取れる条件が保険商品によって異なります。2回目以降の一時金が受け取れる条件が、入院をしていなくても通院が続いていれば給付の対象になるものがおススメです。
・”自由診療”に対応しているか?
最近耳にする機会が増えた”自由診療”に対応しているか?という点もがん保険選びのポイントとなってきています。
3大治療でもなかなか治療の効果がみられなかった場合、「自由診療に挑戦してみたい!」と思う方もいらっしゃるでしょう。ただし、自由診療は、全額自己負担で保険診療と比較して高額な治療法が多いです。そのため、がん保険から自由診療に対するお金が受け取れれば、高額であってもあきらめることなく挑戦できます。とても心強いですね。
・保険料は上がっていくタイプか変わらないタイプか?
将来の保険料も大きなポイントです。
更新タイプのがん保険は若いうちは保険料が安いことがメリットですが、年齢が上がるにつれて保険料が上がります。
特にがんの罹患率が急に高くなってくる年齢に差しかかると保険料もそれに伴い急激に上がります。男性と女性では年齢別のがんの罹患率が違うため、保険料が急激に上がってくる年齢が異なります。特に男性の方は更新タイプだと将来の保険料の負担が大きくなります。たとえば男性は、20代~30代では1,000円代の保険料でも、60代になると10,000円を超える場合もあり、中には20,000円近くになる場合もあります。一方で、女性は男性より若い年齢でがんになる確率が高いため、若い年齢のうちは男性より保険料が高い傾向にあります。ただし、その後の保険料の上がり幅は男性に比べるとなだらかな場合がほとんどです。
ずっと保険料が上がらない終身タイプのがん保険は、更新タイプと比べると若いうちの保険料がやや高くなりますが、保険料はずっと変わらないので将来保険料の負担が大きくなっていくという心配はなくなります。
若いうちは手厚い保障を安く用意しておきたい方は更新タイプ、がんの保障を保険料が上がることなく持ち続けたい方には終身タイプが向いています。自分には何歳までがんの保障が必要か?がどちらの種類の保険に加入するのかの判断ポイントです。
■まとめ
日本人が一生のうちにがんと診断される確率は男女ともに2人に1人以上の確率です。また日本は先進国で唯一、がんで亡くなる人が増え続けている国です。
がん保険を検討するにあたって特に大切なポイントは、今の日本の医療事情にあわせて保障内容を考えること、高額な治療にもあきらめずに挑戦できる権利を持てる保障をつけておくことです。がんから自分自身と家族を守るためのベストな保険はどんな保障をもったものでしょうか?迷った際は1度保険のプロと一緒に考えてみると安心ですね。
WRITER’S PROFILE
なかちゃん 株式会社WDC フィナンシャルアテンダー
元栄養士、ファイナンシャルプランナー。二児のママ。 自身の家族の壮絶な経験から「保険への必要性」「保険で病気と戦える権利をもてる」 をお客さまに説くことを信念とする。 バスケは趣味だが、ガチ。(優勝経験あり。)