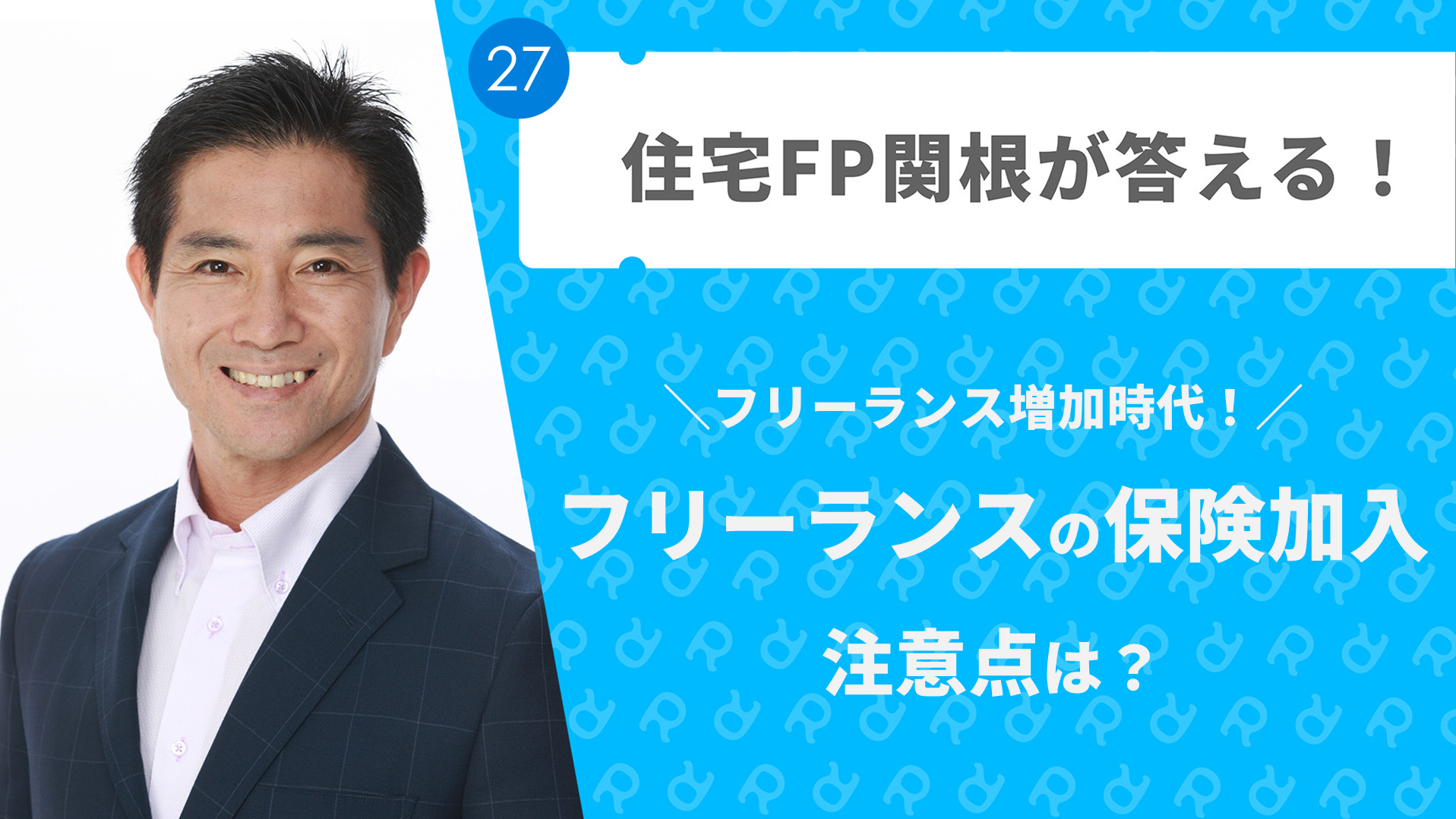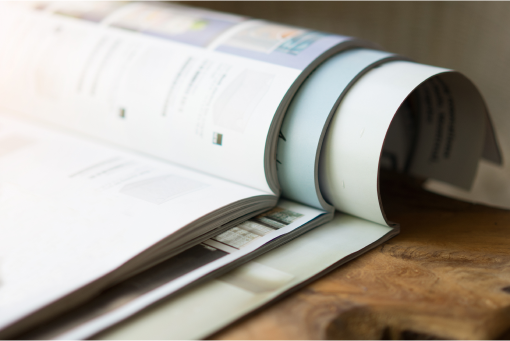生命保険の選び方
2021.12.12
フリーランスの人におススメの保険って?
フリーランスの人は会社員や公務員よりも受けられる公的保障が少ないため、民間の保険を上手に活用する必要があります。
本記事では、フリーランスの人向けに、受けられる公的保障の違いやおススメの保険を解説します。
いざというときに十分な保障を得られるようにするために、本記事を参考にしてください。
フリーランスの人の公的保障
生命保険について考える前に、ここではフリーランスの人が利用できる公的保障の内容について確認します。
会社員や公務員と比較して受けられる公的保障が少ない点を認識しましょう。
国民健康保険
フリーランスの人は国民健康保険に加入します。
国民健康保険でも医療費の自己負担は3割ですし、高額療養費は利用できます。
そのため、医療費に関しては一定の保障が得られていると考えることができます。
しかし、会社員や公務員などが加入する健康保険と国民健康保険の大きな違いは、傷病手当金の有無です。
国民健康保険には傷病手当金がありません。
傷病手当金は会社員や公務員などが加入する健康保険の制度のひとつで、病気やケガなどで働けなくなった際に、直前12ヵ月の収入の約2/3が保障される制度です。保障期間は最長1年6ヵ月です。
フリーランスの人は、この傷病手当金がないため、働けなくなった際の収入減に対する備えを自身で用意しておく必要があるといえます。
国民年金保険
会社員や公務員の人は国民年金保険と厚生年金保険に加入します。
一方で、フリーランスの人は国民年金保険のみです。
フリーランスの人は、国民年金保険であるため、定年後に支給される老齢年金が会社員や公務員の人と比べて少ないです。
また、遺族年金や障害年金の金額が少ない点も忘れてはいけません。
遺族年金:公的年金の被保険者が亡くなった際に、配偶者や子に支給される年金
障害年金:公的年金の被保険者が所定の障害等級に該当する際に受給できる年金
フリーランスの方は、厚生年金保険に加入していない分、老齢年金、遺族年金、障害年金の受給額が少ないです。
そのため、退職後の生活資金、万が一、亡くなった時ののこされた家族に必要な資金、病気やけがで生活や仕事などが制限されるようになった場合に必要な資金に対する備えも自身で用意しておく必要があるといえます。
フリーランスの人におススメの保険
公的保障の内容からフリーランスにおススメの保険を紹介していきます。
ここで、大前提として、保険はご自身にとって必要な保障を得られるように加入する必要があります。
人によって、収入や家族構成、貯蓄額などがさまざまであるため、必要な保障は異なります。
たとえば、扶養する子どものいる人といない人では死亡保障の必要性が違いますよね。
子どものいる既婚者の場合、配偶者や子どもの生活費、子どもの教育費などを踏まえると大きな死亡保障の必要性が高いです。一方で、独身の人や子どものいない人はそれほど大きな死亡保障は必要ないでしょう。このように、ご自身にとって必要な保障を考慮した上で保険を検討することが大切です。
定期保険・収入保障保険
ご自身が亡くなった際や高度障害状態に、のこされた家族が保険金を受け取れる保険です。フリーランスは遺族年金の受給額が少ないことから、死亡保障を充実させる必要があります。
定期保険も収入保障保険も一定期間だけ、大きな保障を割安な保険料で持ちたい方に向いている保険です。
どちらも掛け捨てで契約時に定められた保険期間が満了すると保障はなくなり、満期保険金はありません。いわゆる掛け捨て型の保険です。
定期保険と収入保障保険の違いは、保険金額の推移や保険金の受取方法、保険料の負担感です。
定期保険は、保険金額が満期まで一定で、保険金を一括で受け取ります。
収入保障保険は、保険期間が経過するにつれて保険金額が徐々に減る点が特徴です。徐々に保険金額の総額が減少するため、定期保険よりも保険料が安いです。また、収入保障保険の保険金はお給料のように毎月一定額を受け取れるのが特徴ですが、一括で受け取る事もできます。
医療保険
病気やケガをした際に給付金を受け取れる保険です。
国民健康保険でも、医療費に関しては一定の保障を得られますが、フリーランスは収入が不安定な面もあるため民間の医療保険も活用して備えておくと安心でしょう。
公的医療保険では入院時の差額ベッド代や食事代、先進医療に関する医療費などは対象外で全額自己負担です。
民間の医療保険の給付金はこのような自己負担となる費用に対する備えとして役立ちます。
また、医療保険だけではなく、日本人の多くがなると言われるがんやがんを含む三大疾病などに手厚く備えるために、医療保険に特約を付加することやがん保険や三大疾病保険への加入を検討するのもオススメです。
就業不能保険・所得補償保険
フリーランスの人は、傷病手当金がないため、就業不能保険や所得補償保険で働けなくなった場合の備えを自分で用意しておく必要性が高まります。
どちらも働けなくなった場合の収入を補うための保険です。就業不能保険は生命保険会社が販売、所得補償保険は損害保険会社が販売しています。
就業不能保険は、60歳や70歳までなど長期間にわたって保障をもつことができることが特徴です。保険料は、加入するときの年齢や性別、保険金額、いつまで保障するかによって異なりますが、契約時に定めた満期まで保険料は一定です。
一方で、所得補償保険は、1年更新や5年更新など更新型が基本です。保険料は、加入するときの年齢や職業、更新時の年齢によって異なりますが、年齢が上がるにつれて保険料が上がっていくのが一般的です。
働けなくなった場合の保障をいつまで持ちたいか、将来の保険料の負担などを考慮してご自身にあったものを比較検討するのがオススメです。
終身保険
前述の定期保険や収入保障保険を、貯蓄型の死亡保険である終身保険で加入する選択肢もあります。
終身保険のメリット
・保障が一生涯続く
・保険料が掛け捨てではなく貯蓄性がある
・保険料が加入時点から変わらない
保険料が加入時からずっと変わらないため、若いうちに加入すると割安な保険料を維持できます。
30代で終身保険に加入した人でも、60歳で支払う保険料が加入した当時と変わりません。
年齢とともに、亡くなるリスクや病気になるリスクなどが上がるにつれて保険料が上がるため、保険料が加入当時から変わらない点は大きなメリットです。
終身保険のデメリット
・保険料が高い
・早期解約すると貯蓄の役割を果たせない
・将来的に保障内容が合わない可能性がある
終身保険は貯蓄性があるといっても、早期で解約した際には、解約時に戻ってくるお金は払い込んだ保険料の総額を大きく下回ることが一般的です。
以上のメリットとデメリットを踏まえて、終身保険がおススメな人は、
・保険で貯蓄を考えている人
・計画的な貯蓄が苦手な人
です。
逆に保険料の負担が増えるため、保険料を支払い続けることが負担になる不安がある方にはおススメできません。
個人年金保険
フリーランスの人は老齢年金の受給額が会社員や公務員の人と比べて少ないため、保険や貯蓄、資産運用などで備える必要があります。
そのうちの保険で備える手段のひとつが個人年金保険です。
個人年金保険のメリット
・確実に老後資金を準備できる
・税金の控除がある
貯蓄が苦手な方にとっては、毎月保険料として口座から引き落とされるため確実に準備できます。
加えて、支払った保険料に応じて一定額が所得税から控除されるため、税金の負担を軽減できます。
個人年金保険のデメリット
・インフレになると不利
・途中解約時の元本割れのリスク
モノの価格が上がると、必要なモノやサービスを購入するためにより多くのお金が必要になります。
そうなるとお金の価値が下がるため、個人年金保険で準備した資金だけでは不足する可能性があります。
老後資金を準備する手段は保険だけではないため、他の手段と比較検討した上で、ご自身にとって個人年金保険で準備することが合っている場合に加入しましょう。
まとめ
フリーランスの人は会社員や公務員の人よりも受けられる公的保障が少ない点から、民間の保険で必要な保障に備えることが重要といえます。
しかしながら、人によって収入や家族構成、貯蓄状況がさまざまであるため、必要な保障は異なります。ご自身にとって必要な保障に備えられる保険をしっかり把握して加入することが大切です。
傷病手当金がないことや遺族年金の受給額が少ないことなどから、定期保険や収入保障保険、就業不能保険、所得補償保険は特におススメです。
WRITER’S PROFILE
リアほMAGAZINE編集局
保険選びのリアルな情報やノウハウをシンプルに分かりやすく解説するリアほ編集局です。